
毎年訪れる2月11日は日本の祝日、建国記念の日です。
普通に解釈すると国ができた日なのですが、何をもって建国記念日とするかは各国により異なります。
たとえば、独立や統一という歴史的な出来事を建国記念日とする国も少なくありません。
しかし、日本の場合は「建国記念の日」、真ん中に「の」が入っていますよね。
この違いは重要なポイント!そもそも他の国の建国記念日とは異なってくるのです。
建国記念の日とは?
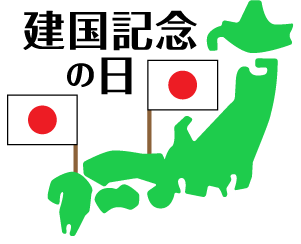
日本の建国を祝う日は、1966年(昭和41年)に政令で定められました。
どんな催しがあるのと訪ねられると、はっきり答えられない方も多いと思いますが、この日は各地の神社や寺院などで建国を祝う紀元祭や建国祭が執り行われます。
ただ、不思議なことに祝日の名称は「建国記念日」ではなく「建国記念の日」、なぜか記念と日の間に「の」が入っているのです。
でも、私たちが普段会話する時は「明日は建国記念日だね」というように「の」を省いてしまいますよね。
なぜ建国記念の日なの?
建国記念日は、その名の通り建国された日なのですが、日本の場合は建国日がはっきりしていません。
その為、建国した日ではなく、「建国をお祝いする日」としました。
法律(国民の祝日)によれば、
・建国をしのぶ日
・国を愛する心を養う日
と定めており、どこにも建国した日とは書かれていません。
祝日の元となっているのは、日本神話に出てくる神武天皇(初代天皇)の即位日、日本書紀によると紀元前660年のことです。
・初代天皇(神武天皇)の即位日=建国記念の日
建国日がはっきりしていない、神武天皇は神話上の人物である、こういった日本の特徴が「の」をつけた理由の一つといわれています。
また、曖昧なのは祝日の表現だけではありません。
建国記念の日は「政令で定める日」とされ、元日や昭和の日のように日付が明確に定められていないのです。
なお、国民の祝日の中には、あと二つ明確に日付が定められていないものがあります。
なんだかわかりますか?
そう!そうなんです!答えは「春分の日」と「秋分の日」です。
こちらは国立天文台が公表するので日付が定められていません。
建国記念の日を祝う行事ってある?

「建国記念の日」って何かやっているの?と思う方は意外と多いのではないでしょうか?
確かに祝日を普段通り過ごしていたなら、お祝い行事を見かけることはないかもしれません。
しかし建国した日ではないとはいえ、色々なところで建国記念を祝う行事が執り行われています。
意外と近いところで、お祝い行事が行われているかもしれませんよ。
都内では奉納パレード
神宮外苑銀杏並木通りからスタートし、青山通り、表参道、明治神宮とパレードが行われます。
参加するのは鼓笛隊や吹奏楽団、そして神輿。
子供から大人まで数千人に上る人たちが、建国記念の日を大いに盛り上げてくれます。
2月11日に開催する代表的な行事の一つです。
大きなイベントですが、知らなかったという人も多いかもしれませんね。
海上自衛隊による満艦飾(まんかんしょく)
自衛艦が祝意を表す行事です。
自衛艦の艦首(艦艇の先頭部分)からマスト、そして艦尾(艦艇の後方部分)まで旗をズラリと並べて掲揚します。
満艦飾は、午前8時から日没と決まっており、建国記念の日だけでなく、天皇誕生日、自衛隊記念日、そして内閣総理大臣が観閲する観艦式でも行われます。
自衛隊に興味がある方なら、何度が見ているかもしれませんね。
神社の紀元祭
建国記念の日になると各地の神社にて「紀元祭」や「建国祭」といわれる行事が執り行われます。
蹴鞠(けまり)、武道、場所によってはパレードを行うところもあるようです。
そもそも建国記念の日は1873年(明治6年)に定められた紀元節(2月11日)が復活したものです。
昔は紀元節祭というお祝い行事が大々的に行われていたようですが、今は同じ名称の行事はなくなってしまいました。
寺院の建国祭
各地にある寺院でも建国記念の日には行事が執り行われています。
神社と違い、寺院の場合は紀元祭ではなく建国祭という名称のところが多いようです。
ホームページなどを開設いている寺院であれば、年間行事として掲載されています。
2月11日にお近くの寺院で何かやっているような雰囲気を感じたら建国記念の日を祝い行事かもしれませんね。
まとめ

建国記念の日というのは、建国した日ではなく建国を祝う日です。
たった一文字「の」が入っただけですが、解釈に大きな違いがありますよね。
でも、この日は各地で祝日行事が執り行われています。
2月11日がたとえ建国した日ではないとしても、日本に住んでいることや日本人であることを実感できる一日だと思いませんか?













