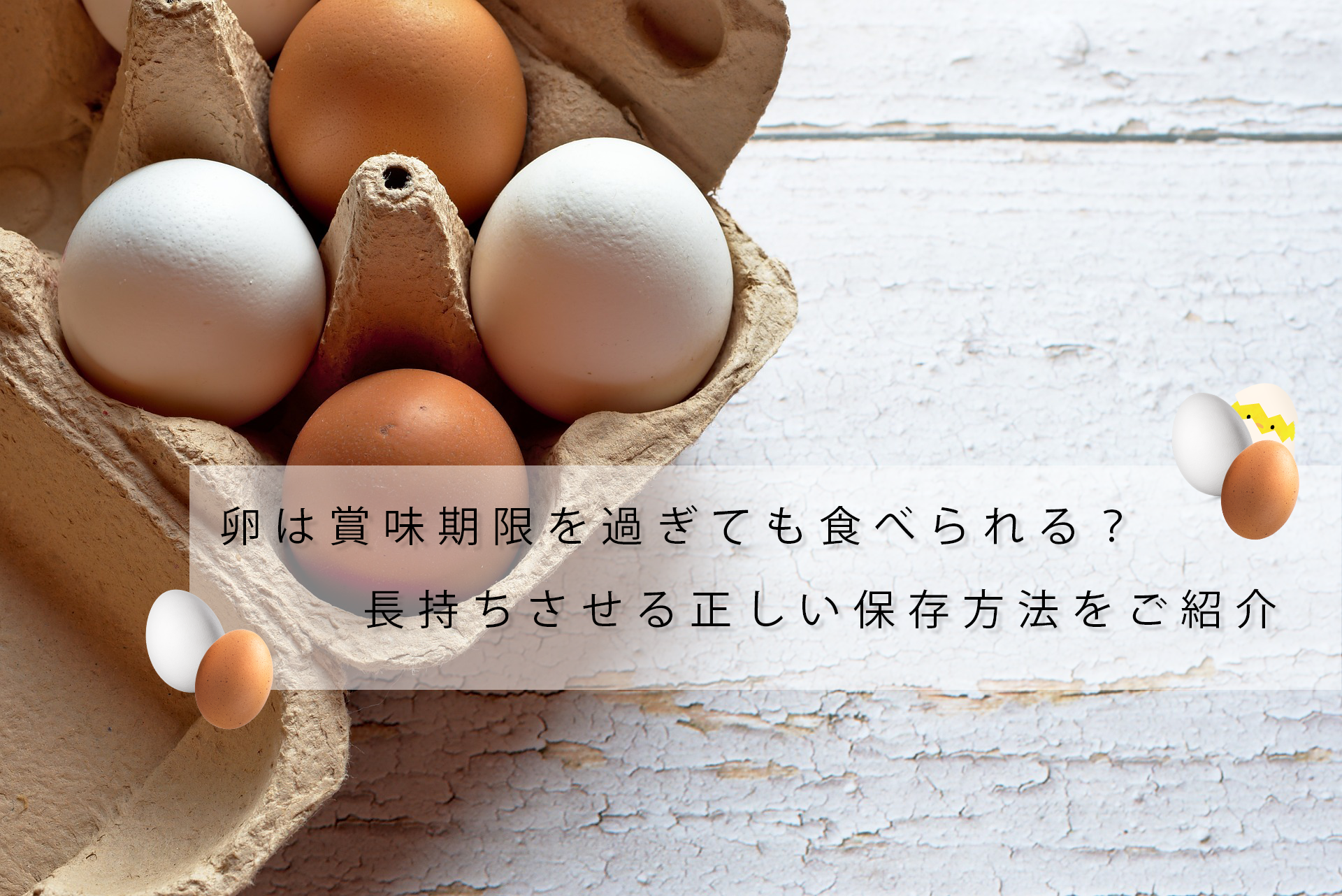一年を通してお店に並んでいるキャベツですが、ちゃんと旬の時期があります。
また、普段は気にせずにキャベツを購入していると思いますが、実はキャベツには種類があって季節によって主に流通しているキャベツには違いがあるのです。
種類によって楽しみ方が異なるキャベツのおすすめの調理の仕方や、ちょっとした豆知識までキャベツに関するお得な情報を紹介します。
実はキャベツには春キャベツと冬キャベツがある

あまり気にしたことがない人も多いのではと思いますが、見た目も異なる2種類のキャベツがあります。
キャベツのイメージにピッタリと一致するのは、冬キャベツでしょう。
外側の葉は薄い緑色をしていますが、内側の葉は白いのが特徴です。
平べったい形をしていて、半分に割ったときの断面は楕円形のように見えます。
一方で、春キャベツの外側の葉は、レタスのような濃さの緑色です。
そして、内側はほんのりと黄色い葉が特徴です。半分に切ったときの断面も丸いので、キャベツのイメージとはちょっと違うと感じる人も多いでしょう。
春キャベツと冬キャベツでは味も違う!
春キャベツの葉は柔らかく、水分をたっぷり含んだみずみずしさが特徴です。
加熱せずにサラダなどで生のまま食べると、春キャベツ独特の甘さを感じることができるのでおすすめです。
また、葉が柔らかいので浅漬けやマリネなど、さっと作れる小鉢料理としても活躍します。
冬キャベツは厚みのある葉が特徴です。
歯ごたえのある触感は、千切りにして揚げ物などの付け合わせとして一緒に食べることが多いと思います。
冬キャベツは加熱することで甘みが強くなり、ボリュームも減るのでたくさん食べられるようになるので、暖かい料理にもおすすめです。
ロールキャベツがとても有名ですが、鍋に入れてもおいしく食べることができますし、キャベツを大胆にくし形に切ってステーキにするという楽しみ方もあります。
キャベツの旬の時期

春キャベツは、秋ごろから種まきが始まります。
そして、4月から6月にかけて収穫を行います。
それに対して、冬キャベツは夏に種まきが始まって、11月から翌年3月ごろまでに収穫を行います。
冬キャベツは加熱して食べるのに向いている食材ですから、寒い冬に食べたい鍋にぴったりの食材と言えます。
千切りキャベツがメインの楽しみ方という人もいるかもしれませんが、是非、鍋に入れるなどして加熱した冬キャベツを楽しんでください。
キャベツの栄養価

春キャベツと冬キャベツで含んでいる栄養価が全く別というわけではなく、どちらも同じような栄養素を含んでいるようです。
主な栄養素としては、ビタミンC・ビタミンK・ビタミンU・カロテン・カリウム・食物繊維などがあります。
食物繊維が豊富に含まれているのは、多くの人が知っているでしょう。
なお、ビタミンCは抗酸化ビタミンと呼ばれていて、皮膚や血管の老化を防ぐ働きがあります。
免疫力を高める働きもあるので、風邪などにかかりにくくなります。
ビタミンKは骨を作る働きを助けてくれる作用と、血液を固める働きです。
ビタミンUは別名をキャベジンと言って、胃酸の分泌を抑える効果や、胃の粘膜を修復する働きがあります。
春キャベツも冬キャベツも加熱せずに生のまま楽しめる野菜です。
熱処理をしてしまうと、壊れてしまう栄養素もあるので、生でも美味しいキャベツは健康維持にもピッタリの食材と言えます。
キャベツの名産地はどこ?

キャベツの名産地を聞かれたら、すぐに答えることができますか。
季節を問わずスーパーで手に入るキャベツですから、産地を気にしたことがない人も多いのではないでしょうか。
国内で最も生産量が多いのは群馬県と愛知県です。
このふたつの県の生産量はほとんど同じで、年によって1位と2位が入れ替わります。
キャベツに関する豆知識

日本にキャベツが持ち込まれたのは江戸時代と言われています。
しかし、当時はキャベツを食べる人はほとんどいなかったようで、本格的にキャベツを食べるようになったのは戦後に洋食は人気になってからだそうです。
ここで、ちょっと面白い話なのですが、シュークリームの名前の由来がキャベツから来ているということは知っていましたか。
シューというのは、フランス語でchouと表記します。
これがキャベツという意味も持っているのだそうです。
シュークリームと春キャベツの形がなんだか似ています。
ただし、シュークリームという名前は日本人が考えたものなので、海外では通じないのだそうです。